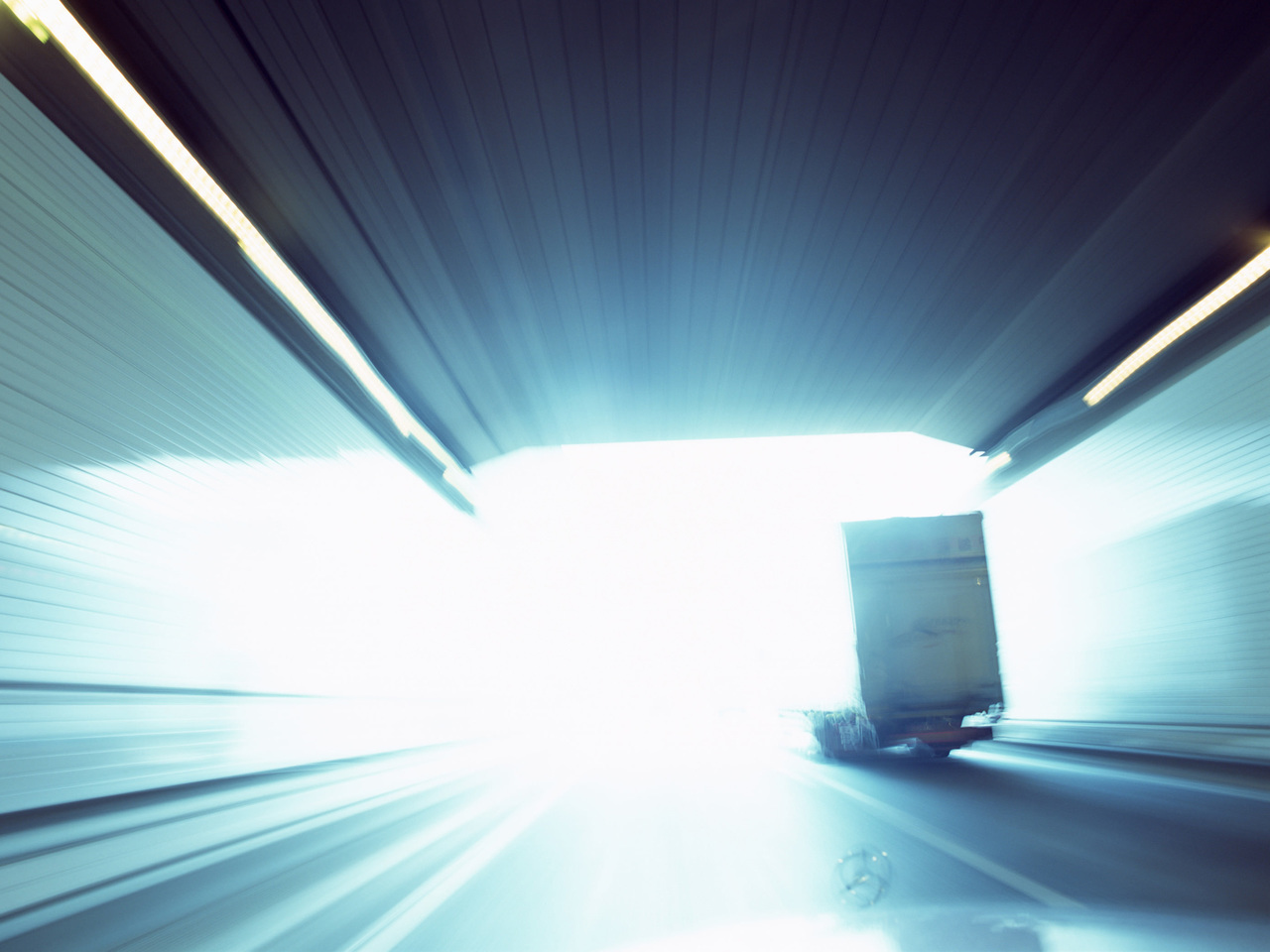静岡県で行政書士をお探しなら
しみず行政書士事務所
ごあいさつ

ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
代表の清水 啓一朗(しみず けいいちろう)と申します。
しみず行政書士事務所では、行政書士・ファイナンシャルプランナー・相続診断士・成年後見相談員などの立場とその知識・経験・スキルを総合的に活かして、お客様のお力になれるよう取り組んでいます。
事業者様に関しては、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、一般貨物自動車運送事業許可などの許可・免許申請や株式会社設立など、事業の開業や発展に寄与できる業務に力を入れています。
行政書士の業務を通じて中小企業の経営者の方と経営状況について話をする機会も多くあり、私の会社生活時代の技術者および経営管理者としての経験や考え方が大変役立っていると感じます。ご希望される経営者の方には、私の方で経営分析書を作成(無料)し、積極的に経営改善についてアドバイスなども行っています。
また、超高齢社会の進行に伴い、相続、遺言、高齢者の財産管理、老後に向けての生活設計、終活への対応などに高い関心を持つ方が増えています。
この様な方々のお役に立てるよう、相続手続、遺言作成、生前贈与、相続の事前対策、家族信託、シニア世代のライフプラン作成などに関する支援・提案などに注力しています。高齢者の方が安心して、笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをいたします。
業務以外の活動としては、公民館が主催する「教養講座」や「高齢者学級」、社会福祉協議会が推進する「地域寄り合い処(地域コミュニティー)」などにおいて、相続・遺言の手続、成年後見制度の活用方法、家族信託、ライフプラン、終活などの講習会講師を積極的に務めています。
相続や財産管理、老後の生活などに関心の高い方や悩みを抱えている方、高齢者や身内に高齢者がいる方などに、分かりやすく説明し、理解して頂けるよう取り組んでいます。

事業経営者様には、事業開設や事業拡大に必須となる以下の業務等の申請手続きや変更届出、実績報告などについて、ご依頼やご相談を承っております。
- 建設業許可
建設工事を請負うには、軽微な工事を除いて、建設業許可を取得していることが必要です。建設業許可の業種には土木一式工事・建築一式工事・各種専門工事の合計29業種があり、工事の内容に応じて対応する業種の許可を取得することになります。
(軽微な工事:請負金額(税込)500万円未満の建設工事、建築一式工事については請負金額1,500万円未満の建設工事又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事)
建設業の営業所が一つの県(都道府県)内にのみある場合は知事許可、営業所が複数の県に設置されている場合は国土交通大臣許可を取得します。
一つの建設工事において、元請事業者が下請事業者に発注する工事代金の総額(税込)が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合は特定工事に該当し、特定許可を取得する必要があります。工事現場には、原則として監理技術者を専任配置する必要があります。
一つの建設工事において、上記の特定工事に該当しない元請事業者の工事や下請事業者の工事を一般工事といいます。この一般工事のうち請負金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の場合は、工事現場に主任技術者又は監理技術者を専任配置する必要があります。(令和7年2月1日改正施行)
・知事許可(一般許可・特定許可)申請
・大臣許可(一般許可・特定許可)申請
弊事務所では、どの業種、どの形態の建設業許可の申請にも対応しています。許可の取得にあたり、許可の要件・基準をクリアする為に何が必要か、どのようにすればよいか等のアドバイスを行っています。また、建設業法、建設業許可の規定等の改正が行われた場合は、お客様へメールで改正内容を分かり易くお伝えするようにしています。
【お知らせ】
・一定の要件を満たすことにより、現場技術者(主任技術者又は監理技術者)が専任の必要な工事現場を2現場まで兼任することができます。 ⇒詳しくはこちら
・一定の要件を満たすことにより、営業所技術者等(旧名称:営業所の専任技術者)が専任の必要な工事現場の現場技術者を1現場兼務することができます。 ⇒詳しくはこちら - 経営事項審査
建設業者の施工能力や経営状況、社会性などを一定の基準により点数化する審査です。国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、この経営事項審査を毎年受ける必要があります。
経営事項審査により付与される建設業の業種ごとの総合評定値は、建設工事競争入札参加資格「格付」の核となる最も重要なものです。
弊事務所では、経営事項審査申請の手続きを代行しています。お客様の毎年の完成工事高・技術者状況・財務内容・各種社会性項目等によって、各建設業種ごとの総合評定値が何点になるか、シミュレーションを行い、経営事項審査の申請前にお客様に提示しています。及び、どの項目をどのように変えていくと総合評定値が向どのくらい向上するかについても、シミュレーション結果をお伝えし、アドバイスを行っています。 - 競争入札参加資格審査
建設工事競争入札参加資格は、国や地方公共団体(都道府県・市町村)など、それぞれ個別に取得する必要があります。
参加資格審査の核となるのは経営事項審査の総合評定値ですが、国やそれぞれの自治体によって独自の「評価基準」が追加設定されています。これらの評価基準をクリアできるようにし、かつ経営事項審査の総合評定値を上げることによって、総合点数がアップし、参加資格の格付(Aランク、Bランク等)を向上させることができます。
弊事務所では、国や地方公共団体などの参加資格審査請求の手続きを代行しています。評価基準のどの項目を改善すると総合点数が何点になり、格付はどのランクになるか等についてアドバイスを行っています。 - 建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の就業履歴・資格・職歴等を国の統一システムに蓄積していく仕組みです。これにより技能者の技能・経験の客観的評価、評価のレベルアップ、処遇の改善、将来の見通しを明確にしていくことなどを目的にしています。
CCUSの要件を満たす工事を行った場合に、経営事項審査の総合評定値に関し加点対象となっています。
今後は、CCUSの要件を満たす工事を前提とした公共工事の発注も増えてくるのではないでしょうか。
弊事務所は、事業者様を代行してCCUSの事業者登録、技能者登録を行っています。 - 電気工事業登録
- 解体工事業登録
- 産業廃棄物収集運搬業許可
産廃が発生する場所(排出場所)、産廃を運び込んで処分する場所(処分場)をそれぞれ管轄する県(都道府県)知事の許可を取得します。排出場所と処分場が同じ県内の場合は一つの知事許可、排出場所と処分場がそれぞれ別の県にある場合はそれぞれの複数の知事許可が必要になります。
許可の申請に当たっては、収集運搬する産廃の品目に応じて許可の申請をします。
また、許可は産廃の危険度によって普通産廃と特別管理産廃に区分されています。
・普通産廃
・特別管理産廃
弊事務所では普通産廃・特別管理産廃どちらの許可申請にも対応しています。及びどの都道府県への許可申請のも対応しています。
許可申請の様式は全国ほぼ統一されていますが、事業計画の記載内容・記載方法については、各都道府県でそれぞれ独自色が出ていますので、その対応が必要です。 - 貨物自動車運送事業許可
- 自動車回送運行許可
- 古物商許可・金属くず商許可
- 酒類販売業免許
- 自動車運転代行業認定
- 宅地建物取引業免許
および - 株式会社設立
- 知的資産経営導入
上記業務のコンサルティング、及び許認可申請・変更届、手続支援、提案などを通じて、事業経営のお手伝いをさせて頂いております。お客様が事業を行う上で困った事、知りたい事などがあれば何でもご相談をお受けし、日頃のお付き合いの中でお客様のお役に立てるよう心がけています。

個人のお客様を対象とした業務では、以下の手続きなどについて、ご依頼やご相談を承っております。
お客様に、手続の内容やアドバイスなど、分かりやすく丁寧に説明させていただきます。ご相談は無料で常時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
個人のお客様を対象とした業務の説明
- 1
相続の手続 の一括代行
ご家族にとっての一大事である相続の発生に伴い、相続の手続きも必要になります。
相続の手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び法定相続人の戸籍謄本の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行い、かつ印鑑証明書等の手続き必要書類一式を揃える必要があります。不動産がある場合は、前記の相続必要書類に加えて登記用必要書類を揃え、名義変更のための相続登記を行う必要があります。
弊所では、ご家族に代わって、戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成など相続手続きを一括代行致します。不動産の名義変更登記が必要な場合についても、弊所が関係先に登記手続きを依頼し完了させる形で、一括代行致します。
また最近は、金融機関の口座の数が多い場合などに、金融機関窓口での手続き簡略化・短時間化のため、法定相続情報証明制度により法務局から交付される「法定相続情報一覧図」の活用が増えています。 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式を基にして被相続人と相続人の相続関係を調査確認して図式化し、これを法務局が認定したものです。戸籍謄本一式の代わりにこの一覧図を銀行窓口で提出することにより、それぞれの銀行側で戸籍謄本一式を調べて相続関係を改めて確認する作業が不要になる為、銀行窓口での手続き時間が短縮されます。 弊所は法定相続情報一覧図の取得手続きについても代行を致します。
- 2
遺言の作成 支援
遺言には、遺産の分割方法の指定だけでなく、ご自分亡き後の家族間の争い等を抑える効果も期待できます。遺言により、法定相続人以外の家族(息子の妻、孫など)や第三者への遺産分割もできます。遺言を活用することにより 、ご自分亡き後の心配事や希望していることについて、ある程度事前に手を打っておくことができます。
例えば、夫婦に子供がいない、障害のある子供がいる、行方不明の子供や配偶者がいる、子供同士の仲が悪い、自分の事業を特定の子供に承継させたい、後妻(現在の妻)と先妻の子供の関係が悪い、等の場合には争いやトラブルが発生しやすいため、遺言を活用した方がよいと思います。
遺言には、主な形式として、公証役場で作成する公正証書遺言と、自分で作成する自筆証書遺言があります。自筆証書遺言については、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言も作成できるようになりました。
弊所では、遺言の内容に関するアドバイスは勿論のこと、公正証書遺言の作成、法務局保管制度を利用する自筆証書遺言の作成についても支援致します。
- 3
ライフプラン(生涯生活設計) の作成支援
お客様の希望する老後の生活(シニアライフ)、安定した老後の生活が送れるかどうかを、お客様の保有資産・今後のお金の収支・今後の行事計画などを基にキャッシュフロー表を作成して検証します。必要とあれば改善策を織り込んで再度検証します。これにより、お客様の希望する老後の生活を実現するための新たなライフプラン(生涯生活設計)が出来上がります。ライフプランにより、老後の生活の方向づけとイメージを掴むことができます。
弊所では、お客様の新たなライフプランの作成を支援致します。
- 4
家族信託 の活用支援
家族信託とは、例えば、高齢者(委託者)が信頼できる自分の子供など(受託者)と信託契約を結び、一定の財産(信託財産)を子供の名義に移したうえで、自分自身や配偶者又は障害を持つ別の子供など指定した特定の人(受益者)の利益の為に、信託財産を子供が代わって管理・運用・処分する制度です。これにより、高齢者などの財産を安全に守っていくことができます。尚、信託財産は、名義上は受託者の所有となりますが、事実上の所有者ではありません。
この他、家族信託には、信託契約の中で、信託終了時に残った信託財産(残余信託財産)を誰が承継するかを指定できる機能(遺言に類する機能)や、最初の受益者が亡くなった場合に次の受益者を指定しておく機能などがあります。
弊所では、家族信託の機能を効果的に活用して、お客様のご希望やニーズに沿った信託契約内容の提案・作成を致します。その上で、公証役場における信託契約公正証書の作成まで一貫して支援致します。不動産の名義変更登記が必要な場合、弊所が窓口となり関係先に登記手続きを依頼し完了させます。
- 5
任意後見 の活用支援
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。どちらも家庭裁判所の審判を経て、支援者が高齢者等の財産管理を行うことができます。
法定後見は、既に判断力が低下した高齢者等を対象に、家庭裁判所の監督のもと、家族(又は専門家)等の支援者が高齢者等の財産管理と身上監護を行う制度です。
任意後見は、高齢者等が、まだ判断力がしっかりしているうちに、家族(又は専門家)等の支援者と公正証書による任意後見契約を結んでおき、判断力が低下した場合に、家庭裁判所の監督のもと、支援者が高齢者等の財産管理と身上監護を行う制度です。任意後見契約とセットで財産管理委任契約を結ぶことにより、高齢者等の判断力がしっかりしている時から、支援者に財産管理を委任することができます。
弊所では、任意後見に関するアドバイス、及び公正証書による任意後見契約書、財産管理委任契約書の作成を支援致します。
- 6
生前贈与の支援
親から子へ、又は祖父母から孫への生前贈与を効果的に又は非課税で行うことのできる各種制度(相続時精算課税制度、暦年課税制度、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与特例)があります。
相続時精算課税制度は、贈与者が子や孫にまとまった金額の財産を、一定額までは非課税で生前贈与でき、贈与者の相続発生時(死亡時)において、贈与と相続の課税関係を一体的に処理・精算・課税する制度です。
1)生前贈与額累計2,500万円までは非課税で贈与できます。(2,500万円を超えた部分は一律20%税率で贈与税を支払います。)
2)贈与者が亡くなり相続が発生した時点で、生前贈与財産と遺産を合計した額に対して、相続税の算出及び支払った贈与税がある場合には贈与税の精算等を行い一体的に税の処理・課税を行います。
※相続発生時において、贈与者の「生前贈与額と相続発生時の遺産額との合計額」が「相続税の基礎控除額」より少ない場合は、贈与税・相続税の納付は必要ありません。
弊所では、生前贈与に関する各種制度の活用方法のアドバイスと贈与契約書の作成を致します。
- 7
夫婦間自宅生前贈与の支援
20年以上婚姻期間のある夫婦の間では、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が夫婦間で行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで合計2,110万円まで非課税となる特例があります。
弊所では、贈与契約書の作成を致します。不動産の名義変更登記については、弊所が窓口となり関係先に登記手続きを依頼し完了させます。
相続の事前対策は、当然ながら、お客様によって事情がそれぞれ異なり、対応も異なります。お客様の希望、目標などをしっかり把握したうえで、お客様にあった対応策を検討する必要があります。
弊所では、相続財産目録を作成したうえで、相続財産の分割方法の検討・検証、及び生前贈与の効果的な活用方法等ついて検討・検証を行い、できるだけお客様の希望、目標に沿える提案を致します。
- 9
終活への対応
終活とは、『人生の後半戦(シニアライフ)を楽しみ、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備をすること』です。(弊所では『終活』をこのように定義しています。)終活を行う上で大切なことは、次のようなことだと思います。
・希望するシニアライフを送るために必要な生活資金が確保できているかを確認し、必要であれば対策を行うこと(⇒ ライフプランの作成)
・身体が不自由になったとき、判断力が低下したときに備えて、事前に財産管理の方法を決めておくこと(⇒ 財産管理委任契約、家族信託、任意後見などの活用)
・最期を迎える準備として、家族に争いが起きないよう財産の分割方法を自分で定めておくこと、家族に知らせておくべき事項を記載して残しておくこと(⇒ 遺言書、エンディングノートの作成)
弊所では、お客様が終活を行うにあたり必要となる事項・作業等の全般について、アドバイス、提案、実行面の支援等を行い、お客様をトータルに支援致します。
- 10
契約書・協議書・合意書 の作成
第三者とのトラブルを未然に防ぐためにご活用下さい。
- 11
自動車の移転登録・車庫証明
ご自分での手続きが難しい方、お忙しい方は弊所をご活用下さい。
お知らせ・お役立ち情報
受託事例・法改正情報
弊事務所の受託した業務の中から、お知らせしたいものを選んで紹介します。

法改正、制度・政策などを紹介します。 【主なもの6件】

スタッフダイアリー
弊事務所の出来事、日常的話題などを紹介します。 【最新作5件】
民法お役立ち情報
民法に関する規定を、身近な事例を通して説明します。 <夫婦、親子、後見、相続、遺言、相隣 関係> 【最新作10件】
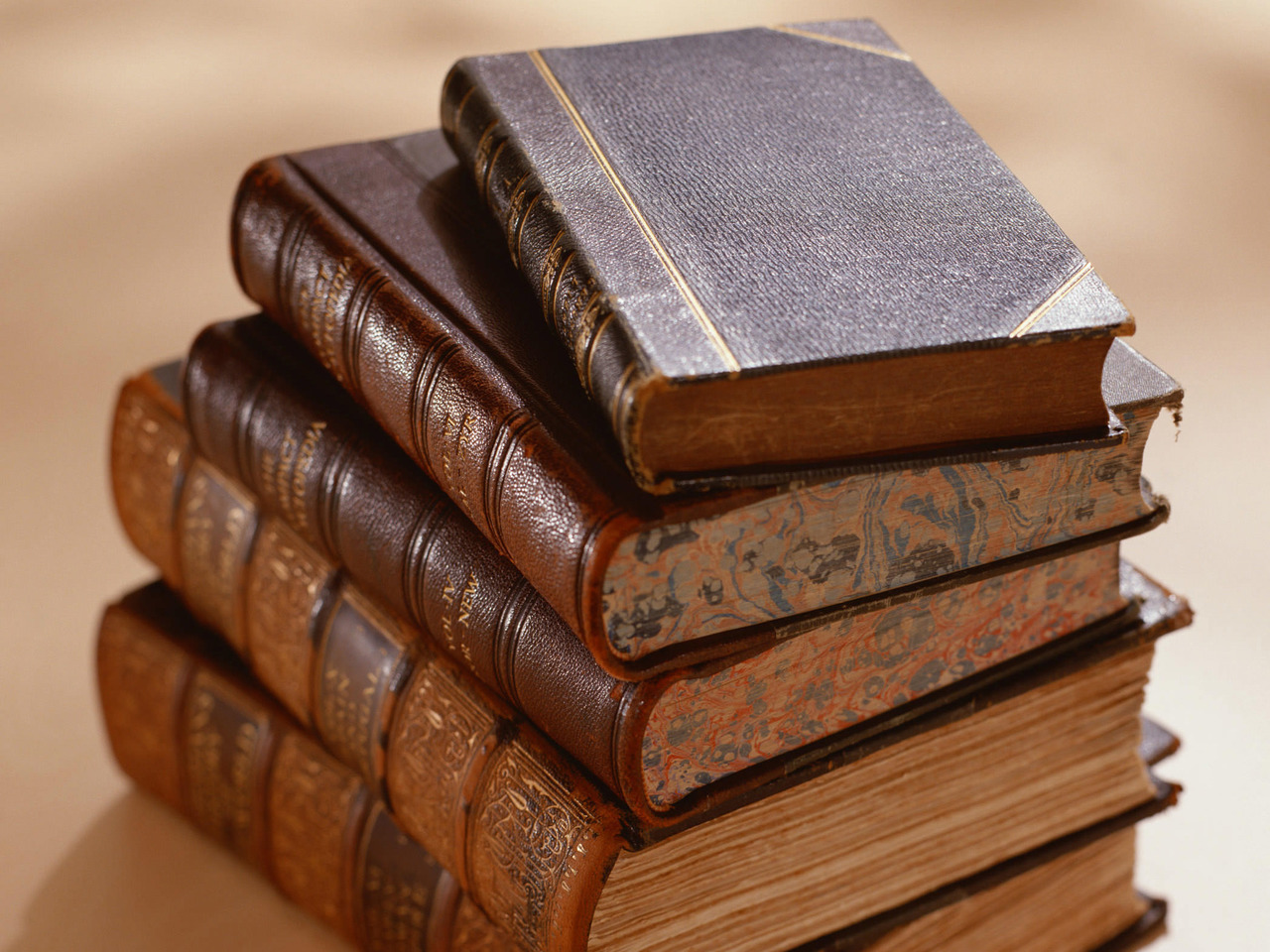
講習会などの活動
講習会などの活動実績の報告です。 【最新の実績】

しみず行政書士事務所の特徴
『お客様の抱える課題の解決に貢献すること』が基本です

弊事務所は、『お客様に心から喜んで頂ける仕事をすること』、『お客様の抱える課題や困っていることの解決に貢献すること』こそが仕事の基本であると考えて、日々お客様と接しています。経験豊富なスタッフが、お客様の要望や解決したいことをしっかりと受け止めた上で、最善の解決策や対応方法について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。お客様が納得できないまま、お話を進めることはありません。
許可の申請業務を得意としています

弊事務所は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、貨物自動車運送事業許可などの許可申請、株式会社の設立など、事業の開設や事業の発展に欠かせない手続を得意としています。経験豊富なスタッフが、許可の取得や会社設立に必要な事項の確認をした上で、各種証明書類の入手も含めて一連の申請手続を全て代行します。どのようにすれば許可が取得できるかなどのアドバイスも致します。お客様にできるだけ時間とお手間を取らせずに手続を進めるよう配慮にしていますので、弊事務所をご活用して頂きたいと思います。
幅広い知識と心遣いでお客様をサポートします

相続や遺言、家族信託、任意後見、ライフプラン、相続の事前対策、終活などに関するご相談は、お客様によって状況がすべて異なります。弊事務所は、スタッフの幅広い知識とスキルをもとに、相続に関する悩み、相続の手続や遺言の作成、家族信託や任意後見を活用した高齢者の財産管理の方法、ライフプランニングによる高齢者の生活設計、生前贈与を活用した家族への財産移転や相続の事前対策、終活の進め方などについて、お客様への支援をさせて頂いております。必要な場合は、他の専門家と連携してお客様の支援を行う体制も整えています。お客様の個人情報に関する気くばり・心くばりにも細心の注意を払っていますので、安心してご相談頂きたいと思います。
免責事項
【免責事項】
当ホームページの内容については細心の注意を持って作成しておりますが、内容の確実性を
保障するものではありません。当ホームページを参考に行動された結果として万一損害が生じ
ても、弊事務所は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
お知らせ・お役立ち情報
事務所紹介
(準備中)
- ≪相続と遺言の規定≫
- 【相続手続の基本事項】
- 【遺言の無い相続手続】
- 相続方法
- 【遺言の有る相続手続】
- 【権利確定の為の手続】
- 【税務の手続】
- ≪成年後見制度の概要≫
- 【成年後見制度】
- 【法定後見】